「笹巻」はもち米を笹の葉で包んで煮た、庄内地方に伝わる「粽(ちまき)」の一種です。
弾力感と深みのある味わいが特徴のもち米「でわのもち」を原料に使用し、灰汁を用いることで生まれるもっちりぷるんとした独特の食感は、ほかに例を見ない伝統料理となっています。
2023年3月には多様な食文化の継承・振興への機運を醸成するために地域で世代を超えて受け継がれてきた食文化として文化庁の「100年フード」にも認定されています。
今回は、清川屋で取り扱っている「三角巻きの黄色い笹巻」を製造している、「農園貞太郎」にお邪魔してきました。
100年フードに認定される笹巻 「農園貞太郎」の挑戦

お話を伺ったのは、代表取締役社長を務める遠藤久道さん。
遠藤さんは2010年に農園を先代から継ぎ、お米や大根などの事業を拡大したその7年後に、山形県庄内地方を拠点として「農園貞太郎」を法人化しました。
恵まれた自然の環境を壊すことなく将来の世代も平和で豊かに生活し続けられる「サステナブルな社会」にするために農業を通して挑戦し続けており、
その取り組みが国からも認められ、農林水産省の「温室効果ガス削減見える化実証企業」で三ツ星認定を認定を受けたお米である「環境配慮米」を産みだした農家さんでもあります。

農作物の栽培が中心の「農園貞太郎」が、笹巻づくりを担うようになったのは、2021年、清川屋の商品部からの依頼がきっかけでした。
上記のとおり笹巻は文化庁の「100年フード」に認定されるほど、世代を超えて受け継がれてきた食文化として注目されている伝統菓子ですが、
注目を浴びる一方で、笹巻の作り手の高齢化や担い手不足による技術継承や材料の確保などが大きな課題となっており、製造技術は年々失われつつあります。
清川屋でも長年お付き合いをしてきた作り手が製造をやめるとの一報を受け、新しい笹巻の作り手として、「農園貞太郎」とは2022年から本格的に笹巻販売のタッグを組むようになりました。

これまで笹巻製造の経験ゼロだった「農園貞太郎」ですが、2024年には講師をお迎えして「笹巻講習会」を行ったり、地域のおばあちゃんたちの笹巻作りの技術を学びながら少しずつ確立させ、日々進化を遂げています。
冬から早春に行われる笹巻の製造は、ちょうど農閑期に手の空いたスタッフを活用する作業としてもマッチしている上に、笹巻を通して庄内の伝統文化や現代の技術を、これからも笹巻が世代を超えて受け継いで行くためにもハイブリッドに残していきたいという気持ち伝えるのに最適。
「いろんなお客様からの喜んでいただける面白いツールなんです。」
と遠藤さんは語っていました。

そんな笹巻の製造に何といっても欠かせないのは、もち米を黄色くし、ぷるんっ!とした食感をもたらす灰汁水(あくみず)です。
灰の種類や濃度、もち米への浸透方法などによってもち米を包む笹やイグサにも影響するため、日々研究しています。
さらに、笹巻の食感は全体が溶けてぷるぷるになっているのが好きな人もいれば、少し粒感が残っているのがお好みの人など、それぞれの地域の味や家庭の味があり、突き詰めると正解がありません。
正解がない中で、代表取締役である遠藤さんが様々な笹巻を食べてきた上でたどり着いた、理想とする「笹巻」は
【良い灰汁水を使い、後味が残らないスッキリとした風味と、糯米の透き通ったプルプルの食感の笹巻】です。
「みんなから美味しいと言っていただけるような味の加減やツヤ感があり、子供から大人まで楽しめる味を追求して、きな粉や黒蜜を添えなくても美味しい、そんな笹巻をお届けすることを目標としています。」
と語る遠藤さん。
実際に「農園貞太郎」の笹巻を初めて食べてみた県外出身の清川屋スタッフMさんからも
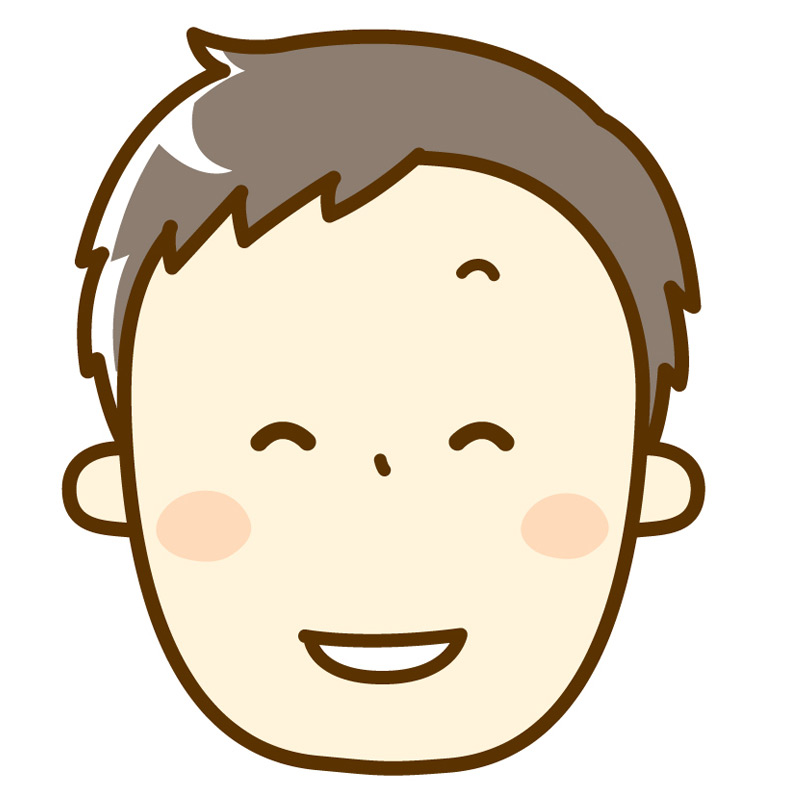
貞太郎さんの笹巻は灰汁感が強すぎずスッキリとしていて、モッチリなめらかな感じ。とても美味しかった。
『何もつけなくても美味しい』と、三歳の子供も、素のまま美味しいと食べていました。
とコメントするほど、「農園貞太郎」の笹巻のクオリティにはこだわりを感じられます。
遠藤さんの思う笹巻とは? 大切にしたいのは「物語」。

笹巻を作る上ではもちろん、原料や資材の高騰、地元の笹の調達が出来ないなど、製造にはさまざまな苦労があります。
特に、笹は笹巻づくりになくてはならないもの。自分たちで調達するには限界があることから、現在は畑の近隣で笹を採取し、自社での保管技術を駆使して生の笹の品質を維持しています。
また、原料であるもち米は100%庄内産を使用しています。特別な注文がある時以外はその日に作ったものを提供しているようです。
製造量についても、昨年はひと月の稼働日が25日間だとして、1日300個、月に換算すると7500個ほど製造された笹巻。
しかし今年は、昨年よりも笹巻の需要が増えたため、より多くの数の笹巻を作るために忙しくなるかもしれない、と語る遠藤さん。
最後に、遠藤さんの思う笹巻とは何か?聞いてみると…

山菜と同じ感じで、旬なもの。
伝統をさかのぼると、端午の節句に子供たちの成長を喜ぶイベントで出したり、灰汁=デトックス商品だと思うので、色んな疲れなどを取り払って、健康を願うようなイベントで食べるような…。

子供のころは何気なく食べていましたが、今考えるとそんな感じだったのかなと思います。
そんな自分がこんないっぱい笹巻を作るようになるとは思ってもみなかったんですけど(笑)
笹巻そのもの、というよりは、笹巻自身が持っている物語や文脈、背景が大切だと感じています。

製造に携わるスタッフは20代から80代までと、幅広い年齢層スタッフが一つひとつ丁寧に作り上げている「農園貞太郎」さんの笹巻。
長い試行錯誤を経て、近年は台湾、中国などの粽(ちまき)や笹巻を食べる文化のある外国向けにも製造するなど、伝統文化と現代技術を融合させた唯一無二の食文化をさらに広めるために、進化を続けています。
「農園貞太郎」の笹巻の美味しさはもちろん、作り手や笹巻自身が持つ物語たちはこれからもより多くの人に届けられていくことと思います。
出来立ての風味がそのまま楽しめる手づくりの笹巻、まだお試しになっていない方は是非、春の風物詩として召し上がってみてくださいね。







